こんにちは、3回転職してから起業したとしです。
退職願も4回ほど出しましたが、毎回苦労しました。というのも、退職願を出した時に、
- 時間がないと断られた
- たのむから考え直してくれと言われた
- この状況で?と怒られた
っていわれたんです。よくあるパターンです。なかなか、すんなりと受け取ってもらえることはありませんでした。
ひどいところになると、何を言っても辞めさせてくれない・・・なんてところもあります。そういうときには、労働基準監督署に行ったり、退職届を配達証明付きの内容証明郵便で出すことです。もしくは退職代行をお願いしましょう。
退職願を出せないときには退職届
「会社をやめよう!」と思ったときに、いちばんはじめに考えるのは退職願をだすことです。退職届は、退職願で退職が決まったときに出すものです。
退職願・退職届の違い
退職願は、会社(あるいは経営者)に対して退職を願い出るための書類であり(ということは、却下される可能性もある)、退職届は、会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類です。(引用:マイナビクリエイター)
簡単に言うと、退職願を出して会社をやめることをお願いして、決まったら退職届を出すということです。
なので、退職願は撤回できますが、退職届は撤回できません。
では、会社側の都合で、
「退職願も退職届も受理してもらえないし、話し合いもしてくれない場合はどうすればいいの?」
とよく聞かれますが、その場合は、退職届を配達証明付きの内容証明郵便で出せば大丈夫です。
退職届を出した日付の2週間後には退職可能
その出した日付の2週間後には会社をやめることができるので、引き継ぎとか自分の荷物の整理をすることです。
これには、ちゃんとした法的な根拠があります。
民法第626条(期間の定めのある雇用の解除)
雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。
民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(引用:ウィキペディア)
正社員の場合、第627条の「期間の定めのない雇用」に当てはまります。
パートとか派遣社員は1年契約とか期間が決められていますが、正社員の場合、いつまでというのは一般的に決められていません。
第627条に書かれてるように、退職の申し出を2週間前にすれば契約終了することができるわけです。
具体的には、月の前半までに申請すると、月末で辞めることができます。月の後半に言い出すと、月給の関係で退職日が翌月末になってしまいます。注意してください。
ただし、就業規則や個別契約によって、退職(解約)の申し出が○ヶ月と決まってる場合があります。
そのときは、その就業規則や個別契約の方が優先されます。3ヶ月以上となってるときは、長すぎるので無効になる場合もあります。
やめようと思って、会社が逃げてる場合は、まずは就業規則を読んでその期間に応じて対処していくことです。
これは、社長などの雇用者とサラリーマンなどの被雇用者の権利が、契約上同じだからです。社長はお金を出して、労働者は体を提供しているわけです。
そこには優劣がないです。
とはいえ、そういった事を説明して配達証明付きの内容証明郵便を出すと説明すると、昔からの中小企業の社長は、怒ってしまい、こちらを脅してきます。
退職願を受理せずに「辞めさせない」と脅してくる時
中小企業や零細企業では、優良なはたらく人員の確保がとても難しいです。仕事のスキルが高い人ほど、社長はあの手この手で引き止めにかかってきます。
- 辞めたら損害賠償するぞ
- 違約金を請求するぞ
- 給料やボーナスは払わないぞ
- 退職金を出さないぞ
- 借金を返すまでは働け
- 今まで迷惑をかけた分だけは働け
- 後任が決まるまでは待ってくれ
- クビにしてやる
- 有給はとらせない
などと言って、聞く耳を持たないことがよくあります。
つまりは、
「おまえはやめさせないぞ」
と脅迫してるわけです。
そんな人ですから、あとから色々と嫌なことをされる可能性が高いです。
そもそも、会社をやめたときには、離職票や年金手帳など次の職場に行くために必要な書類をもらわないといけません。それを出してくれなかったら次の職場に転職する時に困ってしまいます。
そういう場合は、2つのやり方があります。
各市町村にある労働基準監督署に相談
1つ目は、各市町村にある労働基準監督署に相談することです。
各都市の労働基準監督署には総合労働相談コーナーというものがあって、そこに電話して相談してくださいと厚労省も勧めています。全国で379ヵ所あります。
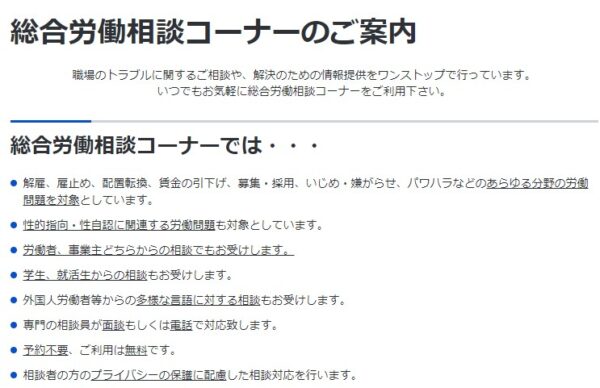
総合労働相談コーナーでは・・・
- 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題を対象としています。
- 性的指向・性自認に関連する労働問題も対象としています。
- 労働者、事業主どちらからの相談でもお受けします。
- 学生、就活生からの相談もお受けします。
- 外国人労働者等からの多様な言語に対する相談もお受けします。
- 専門の相談員が面談もしくは電話で対応致します。
- 予約不要、ご利用は無料です。
- 相談者の方のプライバシーの保護に配慮した相談対応を行います。(引用:厚労省)
まずは、労働基準監督署に相談してみることです。
おそらく上に書かれてる法律と同じことを言われて、配達証明付きの内容証明郵便を送ったり、簡易書留で退職届を送る方法を教えてくれるはずです。
おそらくそれで退職することができるはずです。
ただ、それは「相談」と言うかたちでしかないです。
契約関係は民事の問題なので、労基の方が会社に出向いてあなたの退職届を代わりに出してくれたり、もらうべき書類を代わりにもらってくれることはないです。
しかも円満退社とは程遠い解決策なので、そのあとの処理がとても大変になってきます。
そこで、もう一つのやり方を紹介します。退職代行サービスです。
退職代行サービスに依頼
退職を認めてもらえない会社から退職する2つ目の方法は、退職代行サービスにお願いすることです。
辞めたくても辞めれなかったり、自分で辞めると言いづらいので代わりに言ってもらえるサービスです。
超ブラック企業とか、会社のせいで精神病やうつ病になってしまった方に、とても便利なサービスです。
少し前には、多くのメディアに「良いサービス」だとていよく取り上げられました。
ですが、同時に「かなりグレーな職業です」と弁護士の方たちに言われていました。
「個人が業として行う退職代行や退職代行会社が業として行う退職代行が弁護士法72条違反になるか否かについては確たる判例・裁判例は存在しないものの、弁護士又は弁護士法人以外の者が業として行う場合には弁護士法違反の可能性が極めて高い」(引用:東京駅前総合法律事務所)
弁護士法により、報酬目当てに業務として「法律事務」を行って良いのは弁護士のみとされており、それ以外の人が訴訟や調停、示談交渉などの「法律事務」を行うと違法です(弁護士法72条)。(引用:労働問題弁護士ナビ)
行ってる業務によっては違法ではないかということです。
当時は10個も20個も雨後の筍のようにでてきましたが、今ではすべて淘汰されて、弁護士によるものか労働組合によるものしか残っていません。
弁護士は法律を武器に対抗できますしす。
労働組合は、退職代行などの労働問題において一般法人(株式会社など)と弁護士の強みを”唯一”持つ存在です。
そもそも、労働問題を解決できる力を持っていて、 労働者のために運営されている組織が労働組合ということです。
その中でもおすすめなのは、「退職代行ガーディアン」です。
東京都労働委員会認証の法適合の法人格を有する合同労働組合です。東京都と名前についていますが、全国の企業に対応することが可能です。
詳細は、
- 即日退職可能
- 365日全国対応
- 一律29,800円
- 別途追加費用はなし
- 正社員、アルバイト、パートに対応
朝日新聞や財経新聞を始め、多くのメディアで紹介されています。
詳しくはこちらからごらんになってみてください。
どうしてもあなた自身で退職を切り出せないときに、退職代行ガーディアンはおすすめです。
退職の申し出から書類の受け取りなど、追加料金無しで、今の会社を退職するための手続きをすべて代行してもらえます。
会社の目や親の目、周りの人の目、同僚の目など、気にすることはありません。大切なのは、あなたのこれからの人生と健康です。
今までの会社をきっぱりと断舎離すしましょう。
あなたが笑顔を取り戻せることを応援しています。

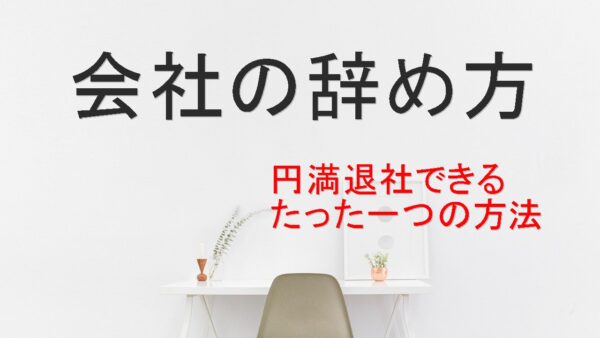

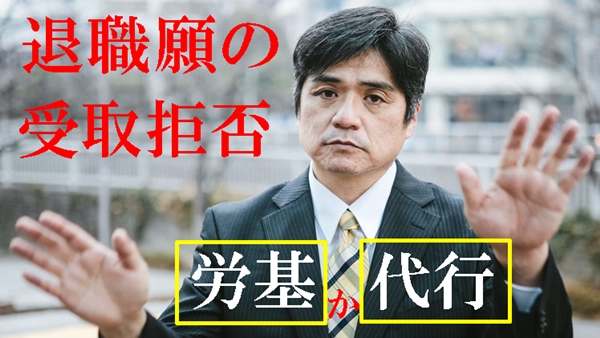
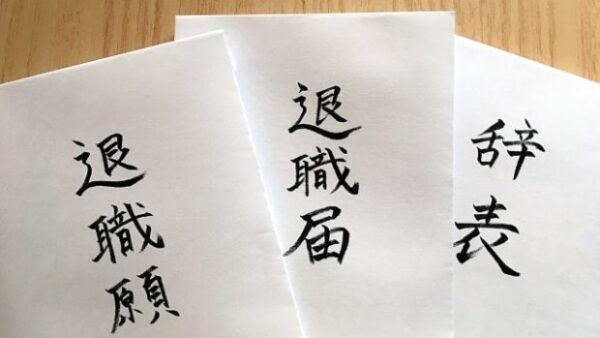

\お気軽にコメントをどうぞ/