
部下を怒らせた経験、ありますか?
部下を怒らせてしまった経験は、管理職なら誰しもがあるはずです。実は、そのときのあなたの対応が、上司としてのあなたの真価を問われた瞬間でもあるんです。
怒らせるようなことを言って部下を育成する時代は過ぎましたし、そもそも、部下が怒ってしまった段階でモチベーションは下がるしやる気もなくなり、それ以上育つわけがないんです。
なので、上司であるあなたは、怒りにまかせて怒ったり嫌味をグチグチ言ったり、ストレス発散のために部下を扱ってはいけないんです。それは同時に、あなたの昇進にも関連します。
部下を上手に育てていくには、部下を怒らせずに効果的に叱ることです。
部下のやる気を削がず、かつ成長をうながす叱り方は、信頼と尊敬を築く上で欠かせないスキルです。
そこで、部下との関係を深め、より良いチームワークを築くためのコミュニケーション術を紹介します。
最後まで読んでもらえれば、わかること
- 部下を怒らせてはいけない
- 部下を怒らせた時の適切な対応方法
- 部下のモチベーションを保ちながら叱るテクニック
- 部下との信頼関係を損なわないコミュニケーションの重要性
- 部下の成長を促す建設的なフィードバックの与え方
部下を怒らせたらダメ!上手な叱り方の秘訣

部下を怒らせたら上司失格!上司としての心構え
部下を怒らせることは、上司としての失格行為です。
なぜなら、怒りは一時的な服従をもたらすかもしれませんが、長期的な信頼関係や部下の成長には逆効果だからです。
上司としての心構えとは、部下のミスや成長過程でのつまずきを、怒りではなく、建設的なフィードバックとして捉えることです。
たとえば、部下が締め切りを守れなかった場合、ただ単に怒るのではなく、その理由を探り、時間管理のスキルを高めるための具体的な支援を提供することが重要です。
ビジネスの世界では、部下一人ひとりの成長が直接的な収益に影響を及ぼすため、怒りによる短期的な成果よりも、教育による長期的な成果の方が価値があります。
このように、怒りをコントロールし、部下のモチベーションを保ちながら成長を促すことが、上司としての真の力量を示します。
なので、いままでの行動や言動を見直して、まずはあなたが部下に対して怒らないことを徹底させましょう。
関連:部下がキレると怖い
なぜ自分が怒ってしまうのか、よく考えることが第一歩
部下が怒ってしまうときって、大体はあなたがはじめに怒ってるはずです。
では、そもそもですが、なぜ自分が怒るのか、考えてみたことがありますか?
相手が間違ったこと、おかしなことをしてるから、自分が怒るのは仕方がない・・なんて思っていませんか?
多くの人はそうかんがえて、アンガーコントロール(怒りのコントロール)をしようと考えます。
でも、アドラー哲学ではアンガーコントロールに意味はなく、「怒りなどの感情は、排泄物なのだ。排泄物を操作しても何も変わらないだろう」と語られています。
どういうことかというと、怒りのもととなる相手の態度とか、言葉にたいして、直接反応して怒るわけではないんです。
怒りのもとになるある刺激が目の前に出てきたときに、まずそれがどういうものか認知して、そこから怒りという感情を呼び起こして、対処してるというんです。
もっと具体的に、心のなかに浮かんだ考えを順番に並べると、
- 部下のミスが起きる
- また失敗した
- 自分の上司からまた怒られる
- もうミスしないようにきつく言わないと
- どうすれば二度としないようになるのか
- そうだ、怒ろう
かなりわたしの解釈も含まれていますが、だいたいこんな感じです。
簡単に言うと、二度とミスをしないように、怒りという感情を全面に出して、部下をビビらせようとしてるんです。
昔、部下を叱っていたときのことを思い出して考えてみると、たしかにそんな意識もどこかにあったような気がします。
そもそも、相手に二度とミスをさせないようにするためには、怒りという感情を出さなくても、理路整然と損得を説明すれば、いいだけですよね。
なぜ多くの人が怒ってしまうのかというと、それが楽だからです。
怖い上司がもっと怖い顔をして「ばかもん」とか「もっとしっかりしろ」なんて怒ったら、すぐにいうことを聞いてしまいますよね。
いろいろ説明するよりも、「ばかもん」の4語で済ませられれば、それに越したことがないような気がします。
でも、それじゃあダメなんですよね。一番初めに書いたように、部下を恐怖で支配するのではなくて、信頼で支配しないとあなたも部下も育つことはできません。
あなたも部下もどんどん育っていくには、怒るよりも叱ることです。
関連書籍:嫌われる勇気
育てるのは怒ることではなく、叱ること
部下を育てるには、怒るのではなく、適切に叱ることが必要です。
叱るとは、部下の行動に対して責任を持たせ、改善を促すプロセスです。
これを理解した上で、叱る際にはPREP法を活用すると効果的です。
まず結論から伝え、その理由を明確にし、具体例を挙げて説明することで、部下は自身の行動を振り返り、次に繋げることができます。
例えば、プロジェクトの遅延が発生した場合、ただ、遅れていると伝えるのではなく、
「プロジェクトの遅延によりクライアントの信頼を失う可能性がある。なぜなら、納期遵守は契約の重要な部分であり、これまでの努力が無駄になるからだ。次回からは、進捗を週に一度報告し、早期に問題を特定できるようにしよう」
と提案することで、部下は具体的な行動変化を図ることができます。
このように叱ることで、部下は自己反省と自己改善の機会を得ることができ、結果として部下の自立と成長を促すことに繋がります。
関連:腹を立てない方法とは?
女性部下を怒らせた時の対処法
女性部下を怒らせてしまった場合、その対処法は繊細かつ具体的である必要があります。
まずは、冷静になるための時間を設けることが重要です。
その後、プライベートな空間で一対一の会話を持ち、感情を尊重しながら話を聞く姿勢を示すことが大切です。
例えば、女性部下が感情的になった原因を理解し、その感情を正当化することから始めます。
そして、具体的な解決策を提案し、今後このような状況を避けるための予防策を一緒に考えることで、信頼関係の回復に努めます。
料金の交渉やプロジェクトの管理など、具体的な業務においても、女性部下の意見を尊重し、彼女たちが安心して意見を述べられる環境を整えることが、長期的な職場の調和と生産性の向上に繋がります。
優秀な人を怒らせたときのリカバリー戦略
優秀な人を怒らせてしまった場合、そのリカバリーには戦略的なアプローチが求められます。
まず、その人の成果や貢献を認めることから始めます。これには、過去の成功例や具体的な数字を引用して、その人の業績を評価することが効果的です。
例えば、「あなたのおかげで、プロジェクトは20%のコスト削減を達成しました」といった具体的な成果を伝えることで、彼らの専門性と貢献を認めることができます。
そして、問題が発生した原因を共に分析し、今後の改善策を一緒に考えることで、相互の理解を深めることができます。
このようにして、優秀な人材が持つ能力を最大限に活かしつつ、モチベーションを維持することが、組織全体の成長に繋がるのです
優しい人を怒らせたら?ショックを避ける方法
優しい人を怒らせてしまった場合、ショックを与えないためには、まずその人の感情を優先して扱うことが肝心です。
優しい人はしばしば自分の感情を抑えがちなので、怒りを表に出さないことが多いですが、内心では大きなショックを受けている可能性があります。
このような状況では、直接謝罪し、その人の感情を尊重することを明確に伝えることが重要です。
例えば、「あなたの気持ちを踏みにじってしまい、本当に申し訳ありませんでした」という言葉を伝え、その後の行動で誠実さを示すことが大切です。
また、具体的な改善策を提案し、その人の意見や感情を今後の意思決定に積極的に取り入れることを約束することで、信頼を取り戻す努力をします。
無視は禁物!優しい人を怒らせた後のフォロー
優しい人を怒らせた後のフォローには、無視することなく、積極的に関わることが求められます。
怒りを表に出さない優しい人ほど、内心では深く傷ついていることが多いため、その感情を無視することはさらなる信頼の損失につながります。
したがって、問題を解決するためには、まずはその人の意見を聞き、共感を示すことが不可欠です。
例えば、
「あなたの立場であれば、私も同じように感じただろう」
と共感を示し、その上で、
「今後はこのようなことが起こらないように、具体的に何を改善すればよいか、あなたの意見を聞かせてください」
と提案することで、優しい人も自分の意見が尊重されていると感じ、関係の修復に向けて前向きなステップを踏み出すことができます。
このプロセスを通じて、お互いの理解を深め、より強固なチームワークを築くことができるでしょう。
部下が怒った時の冷静な対応策
部下が怒った時には、冷静かつ慎重な対応が求められます。
まずは、部下の怒りの原因を理解しようとする姿勢を見せることが大切です。
これには、落ち着いて話を聞くことから始めます。例えば、
「どうしてそのように感じたのか、具体的な状況を教えてもらえますか?」
と尋ねることで、部下は自分の感情を認められていると感じ、怒りが和らぐことがあります。
また、部下の怒りを静めるためには、具体的な解決策を一緒に考えることも重要です。
たとえば、部下が不公平な評価に怒っている場合、評価基準を明確にし、今後の評価プロセスを透明化することで、部下の不安を解消し、信頼を回復することができます。
怒りすぎた部下への適切なアプローチ
怒りすぎた部下に対しては、その怒りを適切に処理するアプローチが必要です。
まずは、部下の怒りを正当化せず、しかし否定もせず、受け止めることが大切です。
これは、部下の感情を尊重すると同時に、問題の核心に迫るためのステップです。
例えば、
「あなたの怒りが理解できます。しかし、私たちには共通の目標があります。どうすればこの問題を解決できるか、一緒に考えましょう」
などと提案することで、部下は自分の感情をコントロールしやすくなります。
そして、具体的な行動計画を立てることで、部下の怒りを建設的な方向に導くことができます。
たとえば、部下が過度なワークロードに怒っている場合、タスクの優先順位を見直し、必要であればリソースの追加を検討するなど、具体的な対策を講じることが効果的です。
おとなしい部下がキレる前に!予防策とは?
おとなしい部下がキレる事態を未然に防ぐためには、日頃からのコミュニケーションが鍵となります。
おとなしい部下は自分の意見を積極的に表明しないことが多いため、定期的に1on1のミーティングを設け、彼らの意見や懸念を引き出すことが大切です。
例えば、月に一度の個別面談を設定し、「最近のプロジェクトで困っていることはないか?」や「職場の環境で改善してほしい点はあるか?」といった質問を通じて、部下の本音を聞く機会を作ります。
また、彼らの小さな成果や努力を認識し、適宜フィードバックを与えることで、部下がストレスを溜め込むことなく、安心して働ける環境を整えることが予防策として効果的です。
職場で怒らせてしまった時の修復テクニック
職場で部下を怒らせてしまった時、その修復には適切なテクニックが求められます。
まずは、部下の怒りの原因を明確にし、その問題を真摯に受け止めることが重要です。これには、部下に対して心からの謝罪を行い、「どのようにすればよかったのか」を部下自身に問いかけることが効果的です。
例えば、「この問題をどう解決すれば良かったと思いますか?」と尋ねることで、部下は自分がどう扱われたいかを表現する機会を得ます。
そして、部下の意見を尊重し、共に解決策を考えることで、信頼関係の修復につなげます。
また、部下の意見が反映された改善策を実際に行うことで、部下は自分の声が聞かれていると感じ、職場のモチベーションと満足度を高めることができます。
不安を感じたら?怒らせたかもしれない時の心得
部下を怒らせてしまったかもしれないと不安を感じた時、その心得としては、まず冷静になることが重要です。
怒らせたかもしれないという不安は、時に過剰な反応を引き起こすことがありますが、その前に一呼吸置くことが大切です。
そして、部下の行動や表情、言葉遣いに変化がないか注意深く観察します。
例えば、普段と違う沈黙や、緊張した様子が見られたら、それは何かを感じているサインかもしれません。
このような時、部下に対してオープンな質問をすることで、彼らの不安や懸念を引き出し、話し合う機会を持つことができます。
例えば、「最近のプロジェクトで気になることはありませんか?」といった問いかけを通じて、部下が抱える不安を共有し、それに対する具体的なサポートを提供することが、信頼関係を築く上で非常に有効です。
部下を怒らせたらダメ!部下を育てる上司の賢い叱り方

- おとなしい人を怒らせないリーダーシップ
- 怒らせた自分を反省、次へのステップ
- 部下育成の極意とは?実践的アドバイス
- 部下を育てる叱り方、使うべきはこれ!
- 部下育成の具体例で学ぶ、成功の秘訣
- 部下の育成に必要なのは愛か厳しさか
- ダメな部下の育て方、間違いとは?
- やる気のない部下を動かす、刺激的な方法
- 自分より優秀な部下を育てる、賢い戦略
おとなしい人を怒らせないリーダーシップ
おとなしい人を怒らせないためのリーダーシップは、細やかな配慮とコミュニケーション能力に依存します。
リーダーとしては、部下一人ひとりの性格を理解し、特におとなしい人に対しては、彼らが意見を表明しやすい環境を作ることが重要です。
例えば、大勢の前で意見を求めるのではなく、個別に意見を聞く時間を設けるなどの工夫が有効です。
また、彼らの意見や感情を尊重し、小さな貢献も見逃さないようにすることで、信頼を築きます。
このようなリーダーシップを発揮することで、チーム全体の士気を高め、おとなしい人も自分の意見が価値を持つと感じることができます。
怒らせた自分を反省、次へのステップ
部下を怒らせてしまった時は、その原因を深く反省し、次へのステップを踏むことが大切です。
まずは、自分の行動や言葉がどのように部下に影響を与えたのかを振り返ります。
例えば、「私のこの言葉があなたにとって不快だったかもしれません」と自己反省の意を示し、部下の感情を尊重する姿勢を見せることが重要です。
そして、具体的な改善策を立て、部下とのコミュニケーションをより効果的なものにするための行動計画を実行に移します。
例えば、定期的なフィードバックの機会を増やす、コミュニケーションのスタイルを見直すなど、具体的な行動を通じて、部下との関係を改善し、より良いリーダーへと成長することができます。
部下育成の極意とは?実践的アドバイス
部下育成の極意は、個々の部下の強みを見極め、それを伸ばすことにあります。
実践的なアドバイスとしては、まず部下一人ひとりとの1対1の面談を定期的に行い、彼らのキャリア目標や職務に対する意欲を理解することが重要です。
例えば、「あなたの長期的なキャリアプランにはどのようなことが含まれていますか?」と尋ねることで、部下の内面にある動機を引き出し、それに合わせた育成計画を立てることができます。
また、部下の成功を公に認め、失敗から学ぶ機会を提供することも極意の一つです。
例えば、プロジェクトでの成功をチームミーティングで表彰する、失敗を経験した部下には、その経験から何を学べるかを一緒に考えるなど、肯定的なフィードバックと建設的なフィードバックのバランスを取りながら、部下の成長を促進します。
部下を育てる叱り方、使うべきはこれ!
部下を育てる際に使うべき叱り方は、励ましと具体的な指導が組み合わさったものです。
中小企業活力向上プロジェクトアドバンスさんのサイトでは、徳川家康の叱り方が書かれていました。
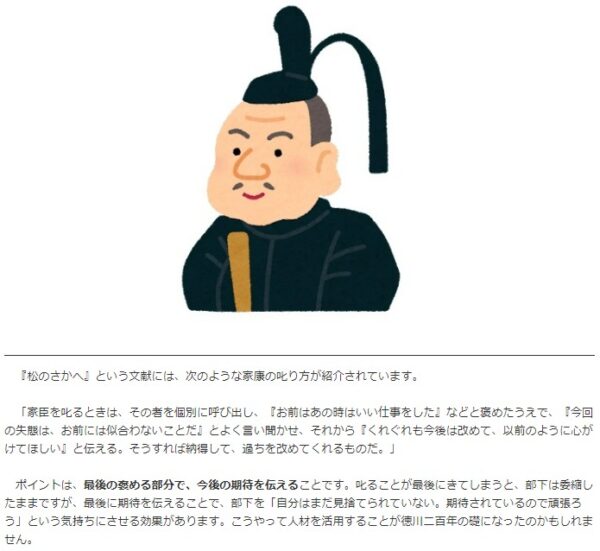
(引用:中小企業活力向上プロジェクトアドバンス)
『松のさかへ』という文献には、次のような家康の叱り方が紹介されています。
「家臣を叱るときは、その者を個別に呼び出し、『お前はあの時はいい仕事をした』などと褒めたうえで、『今回の失態は、お前には似合わないことだ』とよく言い聞かせ、それから『くれぐれも今後は改めて、以前のように心がけてほしい』と伝える。そうすれば納得して、過ちを改めてくれるものだ。」
ポイントは、最後の褒める部分で、今後の期待を伝えることです。叱ることが最後にきてしまうと、部下は委縮したままですが、最後に期待を伝えることで、部下を「自分はまだ見捨てられていない。期待されているので頑張ろう」という気持ちにさせる効果があります。こうやって人材を活用することが徳川二百年の礎になったのかもしれません。(引用:中小企業活力向上プロジェクトアドバンス)
簡単に言うと、褒め言葉と褒め言葉で叱る言葉をサンドイッチにすることが大切なんです。
- ほめる
- 叱る
- ほめる
という順番で話をするということです。たとえば、部下がミスをしたときに、
「ごくろうさん、いつも君のお陰で目標達成できてたすかってるよ。でも、今回のミスはいただけないね。なにかあったのかな。まあそういうこともあるよね。今回のようなことがこれからもあるかもしれないから、しっかりと対策して頑張ってもらいたい。これからも期待してるからね」
という感じでしょうか。
これにより、部下は失敗を恐れずに新しいことに挑戦する勇気を持つことができ、成長への道を歩むことができます。
さらに、部下育成における成功の秘訣は、具体的な行動計画と個々の部下のニーズに合わせた指導にあります。
例えば、新しいプロジェクトを始める際に、部下一人ひとりに明確な役割と目標を与え、それに対する期待を明確に伝えることが挙げられます。
また、部下が目標を達成した際には、その成果を具体的に評価し、次のステップへの動機づけを行います。
成功の具体例としては、部下が自ら問題を解決した場合、そのプロセスをチーム内で共有し、他のメンバーにも学びの機会を提供することが挙げられます。
このように、部下の自立を促し、チーム全体のスキルアップにつなげることが、部下育成の成功には不可欠です。
部下の育成に必要なのは愛か厳しさか
部下の育成においては、愛情と厳しさのバランスが重要です。
愛情だけでは甘やかしにつながり、厳しさだけでは反発を招く可能性があります。
例えば、部下がミスをした際には、そのミスをただ叱るのではなく、「私たちはあなたの成長を信じています。このミスを次にどう活かすかを一緒に考えましょう」というように、部下の自尊心を守りつつ、改善に向けての支援を示すことが大切です。
また、部下が良い成果を上げた時には、その努力を認め、さらなる成長を促すための新たな挑戦を提案することで、愛情をもって厳しさを伝えることができます。
このように、部下の育成には、愛情を持って厳しさを適切に組み合わせることが、部下の成長とチームの成功につながるのです。
ダメな部下の育て方、間違いとは?
「ダメな部下」とレッテルを貼ること自体が、育成の大きな間違いです。
部下が期待に応えられない時、それは彼らの能力の問題だけではなく、上司の指導方法にも原因があるかもしれません。
例えば、部下に自己解決能力を育てる機会を与えずに、すぐに答えを提供することは、彼らの成長を妨げる可能性があります。
また、部下の失敗を責めるだけで、なぜ失敗したのか、どうすれば改善できるのかを一緒に考えるプロセスを省略することも、育成の間違いです。
部下の行動や成果に対して、具体的で建設的なフィードバックを提供し、彼らが自分自身で考え、行動できるように導くことが、正しい育成方法と言えます。
やる気のない部下を動かす、刺激的な方法
やる気のない部下を動かすためには、彼らの内発的な動機付けを刺激する必要があります。
これには、部下が自分の仕事に意義と価値を見出せるようにすることが効果的です。
例えば、部下が関わるプロジェクトが会社や社会にどのような影響を与えるのかを具体的に説明し、彼らの仕事が大きな目的に貢献していることを理解させます。
また、部下に新しいスキルを学ぶ機会を提供することで、自己成長の喜びを感じさせることも有効です。
例えば、専門的な研修への参加や、新しいプロジェクトへの挑戦を通じて、彼らの専門性を高め、仕事への興味を再燃させることができます。
これらの方法を通じて、部下自身が自分の仕事に対する新たな視点を持ち、やる気を取り戻すきっかけを作ることができるでしょう。
自分より優秀な部下を育てる、賢い戦略
自分より優秀な部下を育てるための賢い戦略は、彼らの才能を認め、それを組織の利益につなげることにあります。
まずは、部下の専門知識やスキルを尊重し、その能力を最大限に活用する機会を提供することが重要です。
例えば、彼らに新しいプロジェクトのリーダーシップを任せることで、責任感と自立心を育みます。
また、彼らの意見が組織の意思決定に反映されるようにすることで、彼らのモチベーションを高め、組織全体のイノベーションを促進します。
賢い戦略の一環として、メンタリングの関係を築くことも有効です。自分の経験を共有し、部下が直面するかもしれない課題に対してガイダンスを提供します。
しかし、同時に部下から学ぶ姿勢も大切にし、知識の交換が双方向であることを示すことで、互いの成長を促進します。
このように、部下の成長をサポートし、彼らが組織内でリーダーシップを発揮できるようにすることが、自分より優秀な部下を育てる上での賢い戦略と言えるでしょう。
関連:人生の棚卸しのやり方
参考書籍:部下を育てる
まとめ:部下を怒らせたらダメ!部下を育てる上司の賢い叱り方
この記事のポイントをまとめます。
- 部下を怒らせた場合はまず冷静になり、状況を客観的に評価
- 部下の感情を尊重し、話を聞く機会を設ける
- 部下の怒りの原因を特定し、具体的な解決策を提案
- 部下に謝罪する際は、誠実さを持って行う
- 怒りの感情を和らげるために、適切なタイミングでコミュニケーションを取る
- 怒らせた原因が自分にある場合は、その点を改善する意志を示す
- 部下の怒りを受け止め、改善のためのフィードバックとして活用
- 部下の怒りを未然に防ぐために、定期的なフィードバックを実施
- 部下が怒る可能性のある状況を事前に予測し、適切な対策を講じる
- 怒らせた経験をチーム全体の学びに変える
- 部下の怒りを解消した後は、関係の修復に努める
- 部下の成長と自立を促すために、ポジティブなフィードバックを忘れずに



\お気軽にコメントをどうぞ/