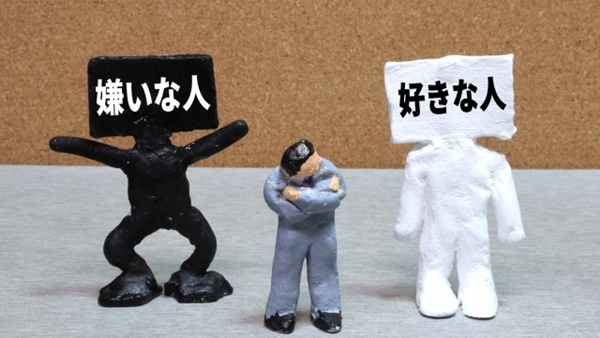
「苦手な人」との関わりは、日常生活の中で避けられないもの。
しかし、その関わり方や「距離を置く」方法を知ることで、人間関係のストレスを半減させることができるのです。
この記事では、そんな「苦手な人との距離の取り方」を中心に、人生をより楽しく、ストレスフリーに過ごすための魔法のような秘訣を大公開します。
あなたもこの方法を取り入れて、日常の小さな悩みやストレスから解放されることを実感してみませんか?
- 人間関係のストレスが人生の質を大きく左右する要因であること
- 「苦手な人」との適切な距離感が心の平穏を保つ鍵であること
- 積極的に距離を置くことで、日常のストレスを劇的に軽減できること
- 人生の質を向上させるための具体的なコミュニケーション術や方法の存在
苦手な人と距離を置く理由と効果的な方法
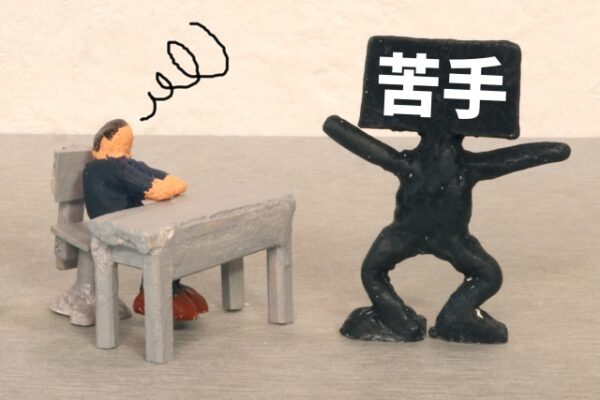
「苦手な人」が生まれる背景と心理
私たちが日常生活の中で「苦手な人」と感じる背後には、複雑な心理的要因が働いています。
これらの要因は、過去の経験や対人関係の中でのトラウマ、そして相手の態度や言動に起因することが多いです。
具体的には、過去に経験した対人トラブルや、自分の価値観と大きく異なる行動をとる人に対して、無意識のうちに警戒心や不信感を抱くことがあります。
これらの心理的な側面を理解することで、より健全な人間関係を築くヒントを得ることができます。
なぜ「苦手な人」と距離を置いた方が良いのか
私たちの日常生活において、ストレスは多くの健康問題や心の不調の原因となります。
中でも、「苦手な人」との対人関係は、ストレスの大きな供給源となり得るのです。
具体的には、苦手な人との関わりによって生じる摩擦やコミュニケーションの障壁は、心の疲れや不安を増幅させる可能性があります。
このようなストレスは、長期的には心の健康を損なうだけでなく、日常の生活の質や仕事の効率にも影響を及ぼすリスクが高まります。
そこで、心の安定や生活の質を維持するためには、苦手な人との距離を適切に調整することが推奨されます。
距離を置くことで、不要なストレスを軽減し、より健やかな心の状態を保つことが可能となるのです。
脳が「苦手」と判断する瞬間的なメカニズム
私たちの脳は、外部からの情報を受け取るたびに、神経回路を通じて瞬時に反応を生み出します。
この反応の中で、扁桃体という脳の部位が中心的な役割を果たしており、過去の経験や学習に基づいて「安全」「危険」といった判断を下します。
特に、過去に受けたトラウマやネガティブな経験は、扁桃体の活動を活発化させ、その人物や事象を「苦手」と感じる感情を引き起こします。
このメカニズムは、私たちが潜在的な脅威から身を守るための自然な防御反応として機能しているのです。
「苦手」という心理が相手に伝わると関係が悪化
人間は言葉だけでなく、身体の動きや表情、声のトーンなどの非言語的なシグナルを通じて感情を伝えます。
特に、「苦手」という感情は、目をそらす、体を向けない、声のトーンが低くなるなどの微妙な行動に現れやすいです。
これらの非言語的なシグナルが相手に伝わると、相手も不快感や不信感を抱くことが多く、結果として関係がますます悪化するリスクが高まります。
このような状況を避けるためには、自分の感情や態度を適切にコントロールし、相手とのコミュニケーションを円滑に進めるスキルが求められます。
「苦手な人」との関係の悪循環を避けるために
「苦手」と感じる人との関係が悪化すると、その関係に対するネガティブな感情や先入観が強まり、さらなる誤解やトラブルの原因となります。
このような悪循環を打破するためには、以下のステップと心構えが有効です。
- 自己反省: なぜその人を「苦手」と感じるのか、自分の中の原因や背景を深く探ること。
- 感情のコントロール: 感情に振り回されず、冷静に状況を判断する能力を養う。
- 相手の視点を理解: 相手の背景や価値観を尊重し、その上でコミュニケーションをとること。
- オープンマインドでのコミュニケーション: 閉じこもらず、相手との対話の場を持つことで、誤解を解消する。
- 適切な距離感の維持: 近すぎず遠すぎず、適切な距離感を保ちながら関係を築く。
これらのステップを踏むことで、「苦手な人」との関係の悪循環を避け、より健全な人間関係を築くことができます。
事象では、これらのことについてもっと詳しく見ていきます。
苦手な人との上手な関わり方とコミュニケーション術

「苦手な人」の5つの特徴
「苦手な人」と感じる原因は人それぞれ異なりますが、一般的に以下の5つの特徴が挙げられます。
- 相手の価値観や考え方が自分と大きく異なる
- 過去のトラブルやネガティブな経験がある
- 相手の態度や言動が自分にとって不快
- 人間関係の中での相手の位置づけが高い
- 相手の存在自体がストレスの原因となっている
これらの特徴を理解し、適切な対処法を取ることで、関係の改善が期待できます。
苦手な人になる原因-メラビアンの法則
相手の事をそのように思ってしまうのには理由があります。
それは、相手の言動です。相手の行動によって、上述した5個の感情が生まれてきてしまうわけです。
では、その言動とはどういうものでしょうか。
心理学上の法則として「メラビアンの法則」があります。
この法則は、人と人とのコミュニケーションにおいて、
- 言語情報 7%
- 聴覚情報が38%
- 視覚情報が55%
のウェイトで影響を与えるというものです。
つまり、相手を嫌いになったり、苦手だと思ってしまうのには、大雑把にかんがえて
- 見た目 50%
- 相手の声 40%
- 話の内容 10%
だということです。
苦手な人と上手に関わっていくことに関して、見た目はどうしようもできないです。
相手の声や話の内容に応じて、あなたができる対処を考えていきます。
相手の声や話の内容で、苦手意識を持つ6つのパターン
あなたが苦手意識を持ったり、嫌いだと思ってしまうひとを、相手の声や話の内容で分類してみると、6つのパターンに分けられます。
- 相手によって態度が変わる
- 自分の間違いを認めない
- 上から目線
- ネガティブな話ばかり
- 話をさえぎる
- 一方的に話す
などの言動をする相手に対して、苦手意識や嫌いだという意識を持ちやすいです。
あなたが苦手だと思う人も、この中に当てはまってるはずです。
それぞれの人に対して、どのように接していけばいいのか、コミュニケーションの観点から見ていきます。
相手によって態度が変わる人の対応策
相手によって態度が変わる人への対応策は、相手の立場を想像して、そういう人なんだと理解することです。
そんな相手に対して、多くをのぞんではいけません。自分にも良い対応をしてもらいたいとは、絶対に思わないことです。思うだけ無駄です。
相手をAIだとかロボットのようなものだと思うことです。
たとえば、上司に向かってはペコペコしていて、お気に入りの部下だけをかわいがってるような女子がいたとします。そしてあなたは嫌われてる派です。
上司「これやっとけ(どうせできないんだろう)」(あなたへ)
上司「これたのむよ。君だったらできる大丈夫だよね」(可愛がってる部下へ)
という感じで言われたときにも、上司に焦点を絞るのではなくて、その仕事に焦点を絞りましょう。
どちらも、仕事をやってくれと言ってるだけです。そして心の中で、
<単純にこの上司はこういう言い方しかできない可哀想な人なんだ>
と思うことです。
自分の間違いを認めない人へのアプローチ
誰しも間違いはありますが、その間違いを認めない人との関わりは特に難しいものです。
このような人との関わり方には、相手のプライドを傷つけないようなアプローチが必要です。
そのためにできるのは、
- 相手を責めない
- 間違ってると伝えない
- そもそも何も伝えない
ことを推奨します。
たとえば、相手がミスをしたとしても、「だめじゃないか」と起こったり、「まちがってるよ」といわないことです。
そもそも、何も伝えなければ、相手との口論や話し合いはなくなります。
そのことでなにか怒ってきたら、すぐに全面的に謝ることです。
「わたしがいけないんです。いいわすれちゃって」
という感じです。面と向かって口論なんかするよりも、謝って数秒で問題が解決できれば、そうしたほうがいいのではないでしょうか。
わたしはそれを推奨します。
上からの目線で接してくる人との関わり方
上から目線で接してくる人も多いです。
いわゆる、マウントを取ってくると言った人たちです。
そういう人たちには、「勝手にやらせておく」ことがとても有意義です。
「はいはい、わかりました」
「すみませんでした」
と言い続けることです。そして更になにか行ってきたら、
「あ、もう大丈夫です。わかりました」
といってその場を離れることです。
基本は、真正面から立ち向かわないことです。
上から目線で言ってくる相手は、あなたを打ち負かしたい、あなたより上だと思いたいわけです。
そんな相手に対して、反論したり、無視したりしてると、相手の思うつぼです。相手はなんとかしてあなたを屈服させようとさらにギアアップします。
そうなると、余計めんどくさくなります。
形の上だけで大丈夫なので、相手の上から目線に乗ってあげることです。
ネガティブな話ばかりする人とのコミュニケーション
ネガティブな話題ばかりする人がいます。
このような人とのコミュニケーションは、あなたのエネルギーを消耗してしまいます。
もしも、その話に乗っかってしまい、相手の背景や心理的要因を理解しようとおもえば、泥沼にはまってしまいます。
こういった相手には、相手には可愛そうですが、適度な距離を保つ工夫をすることです。
いちばん簡単にできるのは、接触回数を減らすことです。なるべく話さないということですね。
その結果、もしも泣きつかれてきたら、ちょっとだけ対処しましょう。
たとえば、「最近避けてるんじゃないの?」と言われたら、「ちょっと忙しくて」とか「なかなか時間が」と言って、すこしだけ話を聞いてあげることです。
こういうひとは、無下に切ろうとすると、逆恨みしてくるので注意が必要です。
もしも、もしもですが、「ポジティブになりたい」と言ってきたら、手伝ってあげることです。
そのときには、ガッツリとダメ出ししたり、「そんな話はするな」と怒れるので、気分が楽になるはずです。
話をさえぎる人とのスムーズな会話の取り方
会話の中で、話を遮る人とのコミュニケーションは難しいものです。
何か話しだそうとすると、「それはね」とか「ちがうんだよ」といきなり横から入ってくる人たちです。
この人たちとコミュニケーションをとるには、こちらが黙ることです。
なにか差し込んできたら、最後まで聞いて上げることです。
話をさえぎる人は、自己主張が強く承認欲求が強い人です。その人達の話をこちらからさえぎろうとすると、怒り出してしまいます。いわゆる口論になります。
プライベートの場合でしたら、聞くだけ聞いてその場をされ去ればいいのですが、仕事ではそうも行きません。
そんなときには、すぐに空いてをさえぎって
「わかりました。ちょっとその話は待ってください。こちらの話をしてから聞きますので」
といって黙らせましょう。
コレが何回も続けば、相手もわかってくるはずです。そのためにあなたに対して悪意を持つかもしれませんが、仕事のためだと思って我慢することです。
これは、上司に対しても同じです。
勇気がいりますが、はっきりと話しの筋道を通して何を話さないといけないのかを、しっかりと伝えることです。
それができなければ、話が終わるまで待って、「で、さっきの話ですが」という感じで元に戻すことです。
一方的に話す人との関わり方
一方的に話をして、どっかに言ってしまう人もいますよね。
こういう人とどうやってコミュニケーションを取ればいいのでしょうか。
この場合は、相手の呼吸を見ることです。
話と話の間とか、文章の区切りのところをしっかりと認識して、すかさず話し出すことしかないです。
そして、
「あなたの言っていたことは、〇〇が〇〇して〇〇ってことでいいですか?」
と再確認することです。
一方的に話をする人は、時間がもったいないという意識がとても強いです。
自分が言いたいことだけを言って、伝わってるかどうか確認せずに、伝わったものだとしてどこかに言ってしまいがちです。
あなたもそれに合わせてあげることです。
余計な話はせずに、要点だけを絞って、「あなたの言いたいことはコレですね」と相手に返事だけさせることで、気に入ってもらえます。
苦手な人との距離の取り方とその重要性
苦手な人」との関わりは、日常生活の中で避けられないものです。
しかし、その関わり方や距離の取り方を適切に行うことで、ストレスを軽減し、より良い人間関係を築くことができます。
また、相手の背景や心理的要因を理解することで、より深いコミュニケーションが可能となります。
最終的には、自分自身の心の平和や日常生活の質を保つためにも、適切な距離感が必要です。
もしも、拒絶反応なんかが出てくるようだったら、すぐに会社をやめましょう。
まとめ:
この記事のポイントをまとめます。
- 距離を置くことで不要なストレスを軽減し、健やかな心の状態を保つことが可能
- 脳の扁桃体が「安全」「危険」といった判断を下し、「苦手」と感じる感情を引き起こす
- 「苦手」という心理は非言語的なシグナルで相手に伝わり、関係が悪化するリスクがある
- 「苦手」と感じる人との関係の悪循環を避けるためのステップと心構えが有効
- 自己反省を行い、なぜその人を「苦手」と感じるのかを深く探る
- 感情のコントロールを養い、冷静に状況を判断する
- 相手の視点を理解し、その上でコミュニケーションをとる
- オープンマインドでのコミュニケーションを持ち、誤解を解消する
- 適切な距離感を保ちながら関係を築く
- 「苦手な人」と感じる原因は、相手の価値観や考え方の違い、過去のトラブルなど
- 日常生活におけるストレスは健康問題や心の不調の原因となる
- 苦手な人との関わりによるストレスは、心の健康や日常の生活の質に影響を及ぼすリスクがある



\お気軽にコメントをどうぞ/